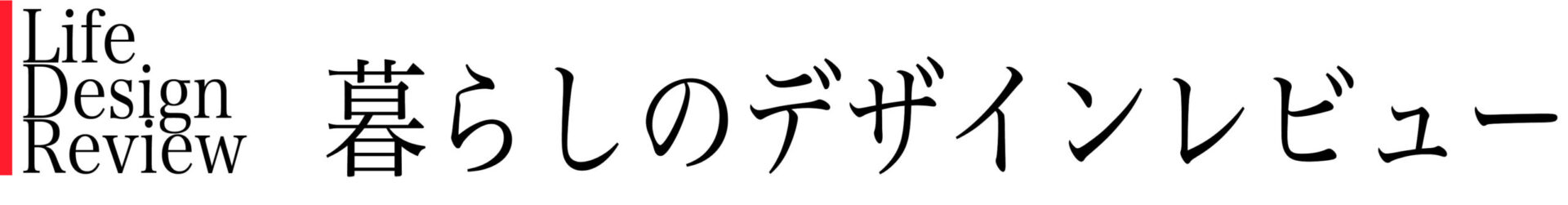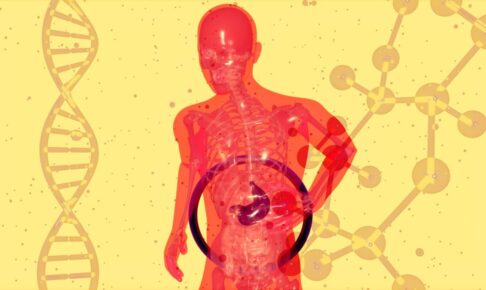画像引用:https://jp.techcrunch.com
アマゾンCEO、 ジェフ・ベゾスを知っていますか?
この記事では、「ベゾス・レター:アマゾンに学ぶ14ヶ条の成長原則」を紹介します。
著者のスティーブ・アンダーソンは、プロのビジネスコンサルタント。そんな彼は、ジェフ・ベゾスについて、リスクを避けるのではなく、それを積極的に組み込んで活用する、“リスクの達人”だと評します。
アンダーソンは、ベゾスが1997年から毎年株主向けに贈っている手紙、通称「ベゾス・レター」の内容を読み込み、アマゾン独特の思考法について分析。そこから、アマゾン急成長の秘訣と思われる“14ヶ条”をまとめたものが、本書「ベゾス・レター」です。
今回は、その中から特徴的な9つを取り上げて、解説をしていきます。アマゾンの秘密を一緒に学んでいきましょう!
1. いい失敗を促す、大きなアイディアに賭ける、ダイナミックな発明や革新を実践する

第1条 いい失敗を促す
アマゾンでは、失敗が最初から予算に組み込まれています。大きな成功を生み出すには、失敗から学ぶことが必要不可欠とわかっているからです。成功の基になった代表的な失敗として、Amazonオプションが挙げられます。
これは失敗には終わりましたが、Amazon 以外の売り手がアマゾンのサイト内で自分の商品を販売することができるというアイディアは、その後Amazonマーケットプレイスに引き継がれ、大きく花開くことになりました。
第2条 大きなアイディアに賭ける
ジェフ・ベゾスは、アマゾンが特に大きな成果を出したサービスとして、マーケットプレイス、プライムサービス、 AWSの3つをアマゾンの柱だと考えています。しかし、いずれも開始前には反対の声が多くあり、うまくいく保証もない大きな賭けでした。
2002年、アマゾンは無料配送というアイディアに着目します。まずは古いスーパーセイバーシッピングという配送日数が増える代わりに、25ドルを超える注文の配送料を無料にするサービスを始め、好評を得ました。
その3年後、アマゾンはさらに大きくかけてAmazon Primeのサービスを開始。年間79ドルを払えば配送料は無料で、商品は最短日数で受け取れます。この賭けは見事に大きな成功を収めました。アマゾンは大きな可能性を秘めているアイディアに最初は小さく賭けて実験し、その後大きく掛けることを繰り返しています。
第3条 ダイナミックな発明や革新を実践する
製品の開発には普通R&D部門など、担当部署を一つだけ儲ける会社が多いです。しかし、アマゾンはそういった方法をとっていません。組織内のあらゆる階層と部署上にいる全員が実験を行うことを後押しし、決して失敗を責めないように徹底しています。
ベゾスは発明を全社員の職務だと考え、アマゾンの成長を促す中核的な原則だととらえています。
2. 自分の弾み車を理解する、決定は迅速に行う、テクノロジーで時間を短縮する

第6条 自分の弾み車を理解する
弾み車というのは、ビジョナリーカンパニー2という本の中で説明されている概念で、回し始めるのは難しいが、ひとたび回り始めればその勢いによってどんどんと成長が加速していくサイクルのことを言います。Amazonのビジネスがどのようなサイクルで 回っているか見てみましょう。
- より多くの商品の価格を下げる
- サイトの訪問者数が増加する
- サードパーティーの売り手が集まる
- 品揃えが広がり配送網が充実する
- 固定費当たりの売上が伸びる
そして、また①に戻るというようにループしていて、このサイクルが回転するたびに効果が蓄積して、ますます大きくなっていきます。本当に偉大な会社では 成功をもたらす要因がある1つの製品ということはありません。
成功をもたらすのは、きちんと考えられた根底にある弾み車の作り方です。弾み車をきちんと設計すれば少なくとも10年、それよりはるかに長い期間にわたって事業を正しい方向に成長させていくことができます。
第7条 決定は迅速に行う
ベゾスは意思決定を、2つの種類に分けました。1つ目は重大かつ後戻りのできない大きな決定で、2つ目は変えることも取りやめることもできる、もしうまくいかなくてもリカバリーができる決定です。
アマゾンは2つ目の種類の決定であれば、社員の誰でもすぐに決定して行動してもいいという企業文化を作りました。
第9条 テクノロジーで時間を短縮する
事業の成長を加速させるものは何か?という問いに、ほとんどの経営者は資金や従業員を増やすことを挙げますが、ベゾスはテクノロジーの活用を最優先に考えています。
AWSはアマゾンが持つ最先端のテクノロジーを誰でも低コストで利用できるようにした革命的な発明でしたが、サービスのリリース後7年間もの間、競合相手が登場しないという幸運に恵まれました。
これはアマゾンが最高のサービスを構築するために十分な準備期間をかけたからこその結果です。AWSは、今なお他の類似サービスよりも先に進んだテクノロジーを提供しています。
3. 企業文化を守る、高水準を重視する、常に1日目だと信じる

第11条 企業文化を守る
Amazonの社員数はたった数人だけだった状態から、60万人以上にまで拡大しました。企業を拡大することの優位性は保ちながら、起業家精神も失わないようにするということに力を注いでいます。
創業間もない1995年当時、オフィスには社員のデスクもありませんでした。デスクを買うためにホームセンターに行ったところで、ベソスは気がつきました。頑丈なドアに足を4本くっつければ、買うよりもずっと安くデスクが作れる。
初期の質素倹約の気持ちを忘れないために、社内の優れたアイディアにはドア・デスク・アワードという賞が贈られ、ベゾスは今なおドア・デスクを使い続けています。
第12条 高水準を重視する
高水準を保つことには、素晴らしい製品やサービスを作れるようになるというほか、に大きな見返りがあります。それは、人は高い水準の人に引き寄せられるということです。ビジネスの世界には、次のような格言があります。
「プロを雇うのは高いと渋ってアマチュアを雇えば、さらに高くつく。」
Amazon の採用面接では、水準の高さを見極めるためのバーレイザーと呼ばれる人との面接が含まれています。バーレイザーは、拒否権を持っていて、その決定には入社後に上司になる人やべぞ術さえ逆らうことができません。
第14条 常に1日目だと信じる
毎年発行されるベゾス・レターには必ず、第1回目のレーターである1997年版のレーターの写しが添付されています。これは、いまもなお常に1日目だというメッセージです。アマゾンが創業時に最もこだわっていたのは、顧客を喜ばせるということでした。この理念はいつまでも変わらないということを、投資家や社員に示すために毎日が1日目であるということを認識させるようにしているのです。
以上、「ベゾス・レター:アマゾンに学ぶ14ヶ条の成長原則」のうち、9つについて解説をしました。本の中では、ベゾス・レターの中で最も重要な第1回目のレターの全文も掲載されていますので、この記事を見て興味を持った方はぜひ実際に読んでみてください!