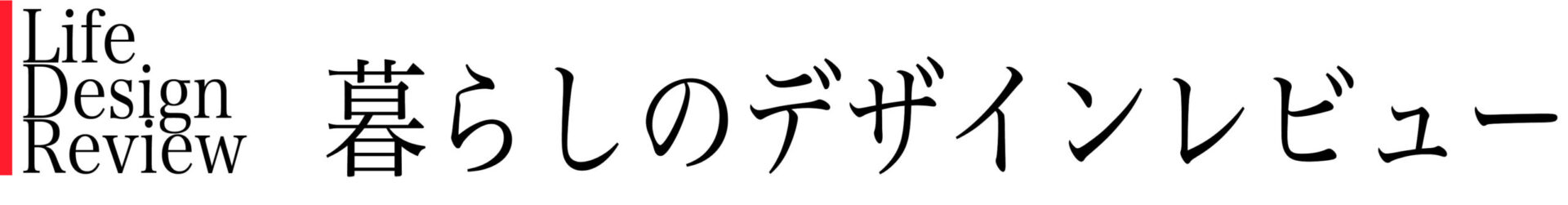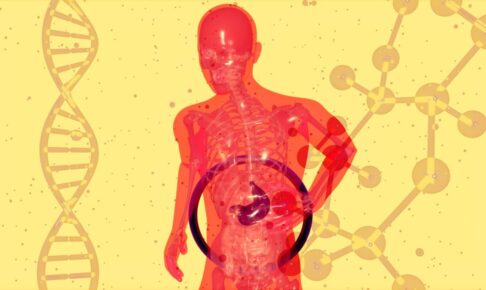毎日の睡眠、満足に摂れていますか?
この記事では、酒谷薫さんの書籍「自分でできる!熟睡脳のコツ」を取り上げます。
ずばり、睡眠不足・不眠を解消し、睡眠の質を上げるには、東洋医学が有効です!
というのが本書の主張。
東洋医学は、中国や日本の伝統医学をベースとしたもので、現代医学や科学とは異なった理論や方法で診療を行います。
東洋医学では、不眠症を“体の不調による未病(病気になる前の半健康状態)”と捉えます。
本書はそんな東洋医学と現代医学の本当にいいところや、効果的なやり方だけを集めて不眠解消法について解説していおり、熟睡生活を送るためにはどうすればいいのかを知ることができます。
それではさっそく、中身をみていきましょう!
1. 自分の不眠体質を知る

睡眠は健康的な生活を送る上で欠かせません。しかし、多くの人が不眠に悩まされています。自分の不眠体質を理解することが、良質な睡眠を取り戻す第一歩です。
まずは、不眠体質を知るための3つのポイントを押さえていきましょう!
不眠症のタイプを知る
不眠症は単に寝付きが悪いだけではありません。
睡眠パターンによって4つのタイプに分類されます。
- 入眠障害:布団に入ってもなかなか寝付けず、悶々とする。
- 熟睡障害:眠っても朝起きた時に疲れが取れた感じがしない。
- 中途覚醒:眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める。
- 早朝覚醒:朝早く目が覚めてしまう。
加齢に伴う自然な現象ならば問題ありませんが、ストレスやうつ病に伴う場合は注意が必要です。
朝日を浴びて睡眠リズムを整える
睡眠改善には朝日が重要な役割を果たします。朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、不眠症状が改善されるのです。その秘密は2つのホルモンにあります:
1. メラトニン:睡眠を誘発するホルモン。光で分泌が抑制されるため、朝日を浴びると日中の分泌量が減り、夜には十分に分泌されて眠りやすくなります。
2. セロトニン:精神を安定させる脳内物質。光刺激で合成が促進され、朝日を浴びることで増加。心の安定につながり、うつ病予防にも効果的です。さらに、セロトニンはメラトニンの原料にもなるので、朝日は一石二鳥なのです。
睡眠不足がもたらす体の変化
睡眠不足の主な原因はストレスです。ストレスによる睡眠不足が続くと、体にはこんな変化が起きます:
- 自律神経のバランス崩壊:交感神経(活動的)と副交感神経(休息的)のバランスが崩れ、交感神経が優位になります。これは車のエンジンをフル稼働させ続けるようなもので、やがてパワーダウンしてしまいます。
- 全身症状の悪化:強いストレスが続くと、食欲低下、体力減退、メンタルの不調といった症状が現れ、不眠症も併発しがちです。
以上の3点を理解し、自分の不眠体質に合わせた対策を取ることで、良質な睡眠を取り戻すことができます。
朝日を浴びる習慣や、ストレス管理は特に重要です。快適な睡眠は健康的な毎日への第一歩。
あなたの体質に合わせた睡眠改善法を見つけましょう。
2. 東洋医学で読み解く不眠体質

現代人の多くが悩む不眠症。
冒頭のとおり東洋医学では、現代医学とは異なるアプローチで心身の健康を捉えます。
ここからは、不眠の原因や対策を東洋医学の視点から、改善する3つのポイントを解説していきます。
現代医学と東洋医学の違い
現代医学(近代西洋医学)は、人体解剖によって見出された臓器の機能に基づいています。一方、東洋医学は「五臓六腑」という独自の臓器観を持ちます。
- 五臓:肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つの臓器
- 六腑:胆(たん)、小腸(しょうちょう)、胃(い)、大腸(だいちょう)、膀胱(ぼうこう)、三焦(さんしょう)の6つの臓器
東洋医学では、これら五臓六腑の働きのバランスが生命維持の鍵だと考え、特に不眠の主要因であるストレスは、「肝」の障害と捉えています。
肝は体内を巡る「気」の流れを調節し、感情をコントロールする役割があるからです。
心身一如、体から心を癒す
東洋医学の特徴的なアプローチは「心身一如(しんしんいちにょ)」の考えです。
これは心と体が一体であるという概念。ストレスで胃腸が弱ったり、肌荒れが起きたりするのは、まさにこの証明です。
実は現代医学にも類似の概念があります。それが「心身症」です。
心身症は、心の障害が体の不調を引き起こす病気で、ストレスが引き金となって喘息やアトピー性皮膚炎などを悪化させます。
東洋医学では、この心身の連携をさらに深く捉え、体を整えることで心の問題も解決しようとします。
不眠体質の4タイプとその対策
現代医学ではストレスが脳に作用して不眠を引き起こすと考えますが、東洋医学ではストレスが体のバランスを乱し、それが睡眠障害につながると見ます。
不眠体質は以下の4タイプに分類されます。
- 肝火亢(かんかこう):
– 症状:ストレスで怒りっぽく、イライラする
– 不眠タイプ:寝付きが悪い(入眠障害)
– 対策:ストレス管理、リラクゼーション - 胆熱上扰(たんねつじょうじょう):
– 症状:肝火亢が進行し、胃腸障害も出現
– 不眠タイプ:入眠障害
– 対策:胃腸ケア、食事管理 - 気血不足(ききつぶそく):
– 症状:疲労感、冷え性。気力と活力不足
– 不眠タイプ:夜中に目覚める(中途覚醒)
– 対策:栄養バランスの改善、温活 - 陰虚火旺(いんきかおう):
– 症状:ホルモンバランスの乱れも影響
– 不眠タイプ:入眠障害、中途覚醒
– 対策:ホルモンバランスを整える生活習慣
東洋医学は、体のバランスを整えることで、心の安定も図る「カラダから治す」アプローチ。
自分の不眠体質を知り、それに合わせた対策を取ることで、心身ともに健康な毎日を取り戻せます。現代医学と東洋医学、両方の知恵を活用して、あなたの睡眠の質を高めていきましょう。
3. ツボマッサージで快眠を取り戻す

現代社会で多くの人が悩む不眠症。
その解消法として注目されているのが、東洋医学のツボマッサージです。
簡単な手技で睡眠の質を高められるツボマッサージの魅力を、鍼灸のプロの視点から2つのポイントで解説します。
鍼灸のプロが教える睡眠障害の自己診断法
睡眠障害を改善するには、まず自分の状態を知ることが大切です。
東洋医学には、簡単に睡眠障害を認識する方法があります。それは「膻中(だんちゅう)」というツボを使う方法です。
- 膻中の位置:左右の胸の真ん中
- 診断法:膻中を指で押して痛みがあるかどうかを確認
- 判断基準:圧痛があれば100%不眠があると判断可能
痛みを感じるということは、そのツボに治療ポイントがあるということです。
では、どのようにこの痛みを緩和するのでしょうか?
ここで効果を発揮するのが、ツボマッサージです。
- ツボマッサージの強さ:痛くなる直前の強さで
- 注意点:痛みすぎると脳が驚いて逆効果になる
ツボが痛いのはストレスの蓄積のサイン。適度な強さでマッサージすることで、ストレスが緩和され、睡眠の質が向上します。
プロが教える熟睡のためのツボ4選
では、鍼灸師が実践する熟睡に効果的なツボを4つ紹介します。これらのツボをマッサージすることで、心身のリラックスを促し、熟睡へと導きます。
- 老衰(ろうこう):手の緊張をほぐす
– 位置:人差し指と中指の間(手を軽く握った時、指先が手のひらにつく間)
– 効果:精神機能に関係し、心身のリラックスを促進
– 活用法:ハンドマッサージに最適。パートナーにしてもらうとより効果的 - 失眠(しつみん):足のストレスを解消
– 位置:かかとの真ん中
– 効果:不眠解消に直結
– 活用法:市販の千日灸(せんにちきゅう)を使用するとより効果的 - 百会(ひゃくえ):頭のストレスを軽減
– 位置:頭頂部(両耳を結ぶ横線と、眉間から頭の中央へ伸びる縦線の交点)
– 効果:頭痛、肩こり、目の疲れにも効果あり
– 活用法:仕事中のストレス解消にも便利 - 安眠(あんみん):その名の通り安眠を誘う
– 位置:耳たぶの後ろ、骨の出っ張りから指1本下
– 効果:眠気を誘発
– 注意点:痛みやすいので、優しくマッサージする
これらのツボマッサージは、寝る前だけでなく日中のストレス解消にも役立ちます。
自分に合った方法を見つけて、快適な睡眠生活を手に入れましょう。
本記事で紹介したツボ以外にも、熟睡に効果的なツボがあります。詳しくは関連書籍をご参照ください。
ツボマッサージは手軽で効果的な不眠解消法。自分の体と対話しながら、東洋医学の知恵を生かして、心地よい眠りを取り戻しましょう!
今回紹介した、酒谷薫さんの書籍「自分でできる!熟睡脳のコツ」について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください!