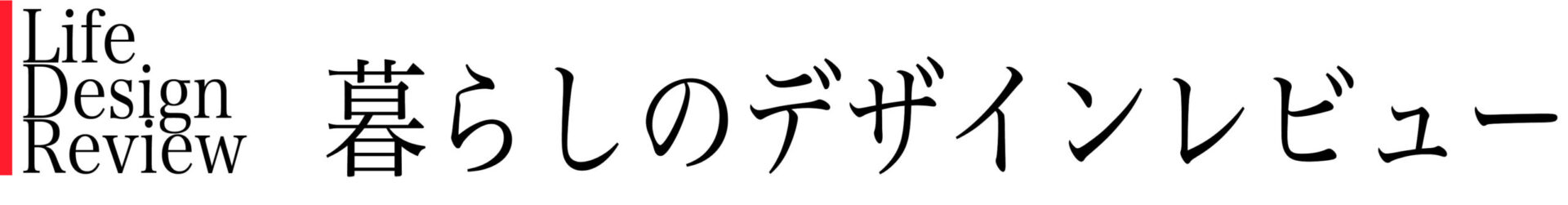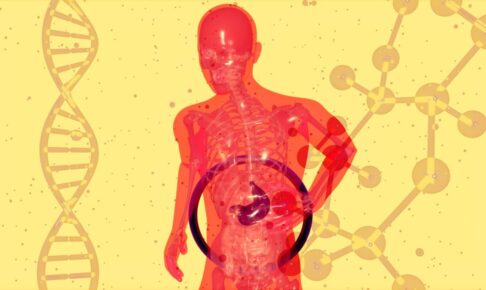日本の企業はオワコンなのか?
この記事では、橘玲(たちばなあきら)さんの書籍「働き方2.0 vs 4.0」を紹介します。これ読むと、なぜ日本企業はオワコンなのか、そして日本に生きる私たちは、これからどう働けばいいのかが理解できると思います。グローバル企業と同じやり方で戦っていても勝てる気がしないなら、戦術を変えるしかないですよね。まずは、本書のエッセンスを理解していきましょう!
1. 日本の企業で起きていること

GAFA(ガーファ)を知っていますか?
Google、Apple、Facebook(今はMetaになりましたね)、Amazonの頭文字のことで、いわゆる巨大プラットフォーマーと呼ばれています。GAFAのような巨大テック企業は、ネット時代で検索、SNS、ECといった分野で圧倒的なシェアを獲得し、市場をどんどん支配しています。そしてまさに今、このGAFAが日本の企業から若くて優秀な人材を次々と引き抜いているのです。
日本の超エリートの一部のみを、超高額報酬で引き抜く。さらに、日本の大手IT企業で働いている優秀な人たちの中にも、将来的にはGAFAにいきたいと思っている人たちは大勢います。GAFAがなぜここまで優秀な人材を獲得できるかというと、影響力の大きさだけでなく、快適な職場環境を提供しているから。無料の食堂やフィットネス、瞑想ルームといった、快適すぎるグーグルのオフィスなどは有名ですよね。仕事で圧倒的な結果を生み出すための職場や研究の環境づくりが、日本とは圧倒的に異なるのです。
海外企業との差は広がるばかり
優秀な人材が流出すれば、当然、仕事の効率も大幅に変わってきます。かつて日本では、大企業に就職することを目的とする人が多くいました。その目指すべき大企業が、いまや海外の大企業にとって代わられ、日本から優秀な人材がどんどん海外に流出しているのです。これからもどんどん日本の企業は弱っていき、GAFAのような巨大テック企業はその勢いをどんどん拡大しています。
現在、日本の企業はまだ何とか保っていますが、将来的にGAFAなどの海外の巨大テック企業に飲み込まれることは明らかでしょう。それが何年先になるかわかりませんが、10年もすれば誰の目にも明らかになると橘さんは指摘します。
2. 日本の企業は素人チーム

日本企業が、GAFAなどの巨大テック企業に勝てない理由を分かりやすく例えるなら、GAFAはプロのスポーツチームで、日本の企業は素人チームだからです。具体例をみてみましょう。
みなさん、ネットフリックス(Netflix)を知っていますよね? ネットフリックスは、定額で映画やドラマをオンラインで楽しめるサービスの1つ。しかしサービス以上に企業の中身としては、他とは違う常識外れた様々な経営戦略を行っています。
まず、日本や世界の企業から極めて優秀な人材だけを引き抜き、すべてのポストに引き抜いた優秀なプロを採用し業界最高水準の報酬と環境を与えています。一方で、たとえ会社に貢献するモチベーションがあっても、成果を残せなければ、辞めてもらうというスタンスをとっているのです。
↓ 以前にこちらの記事で詳しく書いているので、合わせて読んでみてください。
会社は家族ではない
解雇は冷たい仕打ちでしょうか? しかし、世界基準では当前のことです。なぜなら、席に空きがなければ、優秀な人材を見つけても雇うことはできません。“会社は家族ではない”という考えは、世界基準なのです。
それはプロのスポーツチームのようなもので、トップを狙うのであれば、最高のプレーヤーを引き抜いで最高のチームを作れなければならない。プロ野球の業界でも、優秀な選手をチームに獲得するために何十億円という年俸を用意して、最高のチームをづくりをして優勝を目指していますよね? ビジネスの世界でも同じです。
それに対して、日本はどうでしょうか。日本の企業は、未だに時代遅れの年功序列や終身雇用。日本の企業はビジネス環境がどれだけ変化しても、たまたま新卒で採用した社員だけで、なんとかやりくりしようとしています。
海外はプロジェクト責任者を外部から招く
海外では、新しいプロジェクトを開始する時に、その責任者を外部から招き、プロジェクトのチームのリーダーに配置します。そうすることで、プロジェクトが円滑に進んで最大の成果が出せる。一方で、日本ではプロジェクトの責任者を外部から呼んだり、中途採用したスタッフのみでチームを作ることができない構造となっています。そのため、貧しい人材プールから適任者を探そうとしますが、そんな都合のいい話はありません。
例えば、広告代理店は、急速なインターネットの普及によって、媒体がシフトしたために、従来のビジネスモデルを変える必要に迫られました。この時、GAFAなどの巨大テック企業は、まずインターネット広告に精通した人材を外部から引き抜き、プロジェクトのトップに置きます。
一方で日本では、ネット広告について何も知らない素人の新人が配属されたりして、また同じく素人同然の上司に振り回され、ただただ長時間労働・長時間残業を強いられたりします。
野球で例えるなら、普段ピッチャーをしている人に、「ちょっと次の試合ではサードを守ってみてよ」とか、「次の試合ではセンター守ってみてよ」と言っているようなもの。その結果、自分の専門外以外の仕事をやらされて、自分のパフォーマンスを発揮できず、生産性が低下しているのです。
3. これからどう働けばよいか

ここまで、暗い話になっていましたね…。まずはこの事実を認識したうえで、これからどう働いていこうかということを考えてほしいと橘さんは言います。その際に取りうる一つの手段が、日本企業に依存するのではなく、個人で仕事をする“フリーエージェント”です。
これは簡単にいうと、好きなこと、得意なことを仕事にするということ。好きなことで生きていくというと、そんな甘いことが通用するはずないという批判が必ず出てきますが、そのような人たちは労働とは生活のための必要悪であり、苦役であると考えているためです。その考えのままでは、人生100年時代と言われている現代において、20歳~80歳までの少なくとも60年間は、労働という苦役をやり続けなければならないです。
会社に雇われない生き方
著者は、日本企業がGAFAなどの前に崩れ去っていく時代には、原理的に好きなこと・得意なことでマネタイズして生きていくほかはないと言います。もちろんすべての人が好きなことで生きていけるわけではありません。そう聞くと、大半の人は好きなことを仕事にする“フリーエージェント”になんてなれないと思うかもしれませんね。しかしアメリカでは、すでに全就労者数の4分の1がフリーエージェントです。そして、この傾向はねどんどん加速しているそうです。アメリカでは、会社に雇われない生き方が一般化してきているということです。
実際にフリーエージェントが一般化している国が存在すると、できなくはないのかなという気はしてきませんか? “好きは努力に勝てない”というのは、イチロー選手の言葉です。
- その仕事が好きでいくらでも努力ができる人
- その仕事が好きでもない報酬だけで頑張ろうとする人
どちらの人が最終的に勝つかは明らかでしょう。フリーエージェントの考え方について、こちらの記事でより詳しく解説しています。合わせて読んでみてください。
今回の紹介は、ここまでです。橘玲(たちばなあきら)さんの書籍「働き方2.0 vs 4.0」の内容をより詳しく知りたい方は、ぜひ本書も手にとってみてください!