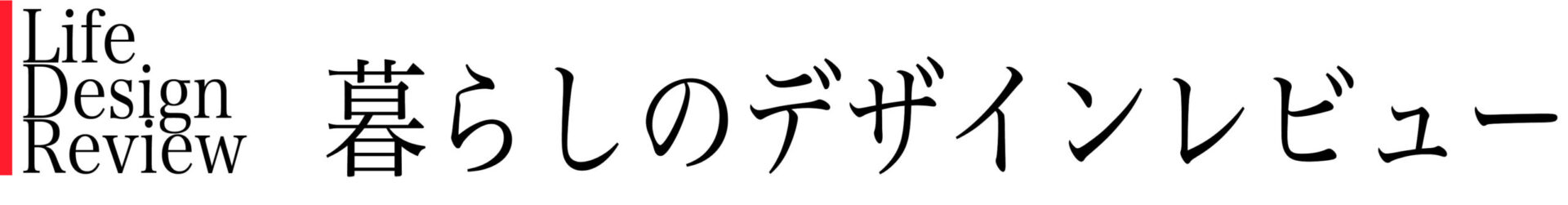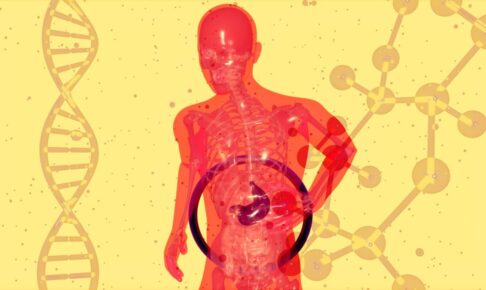日々のストレス、上手くコントロールできていますか?
ストレスは付き合い方によって、頼もしい味方にもなり得ます。
そこで、この記事では、青砥瑞人(あおと みずと)さんの書籍「ハッピーストレス」を取り上げます。
本書は、
- ストレスのことを知りたい
- ストレスとしっかり向き合いたい
- いま心に余裕がない
- 幸せを感じやすくなりたい
という方におすすめで、最先端脳科学でわかった事実を基に、ストレスを味方につけて最高のパフォーマンスと最高の人生導く方法が書かれています。
そもそもなぜ生物、人類にストレスという反応が備わったのか?
それには、どんな意義や役割があるのか?
神経科学や心理学などの知見から解明し、ストレスを私たちの日常生活と結びつけてくれる良書です。
ストレスをなくすことは、できません。
また、ストレスにはネガティブな面だけでなく、私たちの成長や幸せにも貢献してくれる面もあります。
それでは、ストレスとうまく付き合っていく方法を、一緒に学んでいきましょう!
1. ストレスと向き合う第一歩
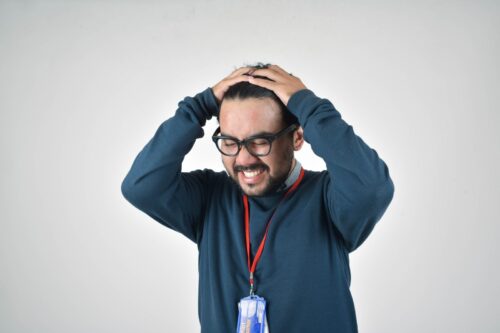
ストレスと聞くと、どうしてもネガティブな印象が頭に浮かびますよね。
ストレス反応は生物、人類にとっての自然摂理の一部であるため、無くすことはできません。しかし、全てにおいてネガティブであるわけではありません。
神経科学という自然科学の観点から見ると、ストレスは厄介なだけのものではなく、魅力もたくさんあることがわかってきています。
だからこそを、ストレスとうまく付き合っていく必要があります。
外側の刺激を減らす
まず大切なことは、ストレスなことからいったん離れること。
なぜなら、私たちの意識の向け方自体が、ストレスに大きく関係しているからです。
仕事の資料、勉強の教科書、周りにいる先生や親、上司や部下、お客さん。はたまた飲食物、パソコンやスマートフォンまで、私たちは日常生活の中でいたるところに注意を向けています。
これらの人やモノは、自分の外側にあるものですが、私たちの注意の対象は外側だけではなく、内側にもあります。
お腹の減り具合、眠気、いま考えていること、感じていること、過去の経験を振り返る時間、未来を創造している時など。
一日を振り返ってみると、内側より外側に注意を向けていることの方が、圧倒的に多くないでしょうか?
一方で、私たちの学びは自分の内側に蓄えられるため、内側に注意を向けずに外側の刺激をただ浴びている状態では、成長を止めてしまいます。
さらには、幸せを奪う可能性すら秘めています。
幸せは内側にある
外側の刺激を減らした上で、入ってきた外側の情報を内側の情報に変換し、内側の情報として引き出すことで、その外側の情報は学びとなります。
私たちは、幸せはどこか外側の世界にあると思い込みがちですが、幸せの反応は間違いなく私たちの内側で起きています。
本書のテーマでもあるストレスも、まさに私たちの内側で繰り広げられるものです。
ストレスと上手く付き合っていくためには、外側の世界的にとらわれないこと。内側の世界、つまり自己と対話していく必要があります。
それが、ストレスと付き合う第一歩です。
2. ネガティビティ・バイアス

私たちはポジティブなことよりも、ネガティブなものに優先的に注意を向きやすい性質があります。
この特徴を、“ネガティビティ・バイアス”と言います。
これは、何万年もかけて進化してきた脳機能の一つで無くすことはできません。
ネガティビティ・バイアスは至極当然の生物的反応であるため、自分はダメだと悲観する必要はないです。
そのため、ネガティビティ・バイアスを受け入れ、少し意識的にポジティブな面にも注意対象を向けるという心がけが必要です。
むしろ自分を改善するための学び、成長の機会であると認識すべきなのです。
大変なことをしない
ネガティブな感情に囚われそうになる自分を、意識的にポジティブに引き戻す俯瞰的なもう一人の自分を持つことが、ネガティビティ・バイアスと共存し成長していくためには重要です。
そこで、まず大切になるのは、大変なことをしないことです。
なぜなら、今そこにあるネガティビティ・バイアスに対して、今日からすぐ変わるような魔法は存在しないから。
変わるには、毎日の心がけや習慣が大切です。
大変だと思うことに手を出しすぎず、少しでも続けられることから始めましょう。
毎日何かポジティブなことを紙に書き出す、人に話したりするといったこともネガティブをなくすためには効果的です。
しかし、環境と時間の問題でこれを続けられない可能性もありますよね。
そんな時はまず日常や自然から、ささやかなポジティブな側面を見いだす。それを少し時間をとって味わうことをしてみてください。
例えば、
- 空は本当に面白い
- 晴れていればそれだけでも気持ちがいい
- 青空にもいろいろな濃さがある
- 青には見えない青空もある
- どの雲一つとして形状は同じではない
など。
このように日常の中にあるポジティブな情報に、少しずつ意識を向けることが大切です。
3. ストレスの構造を知る
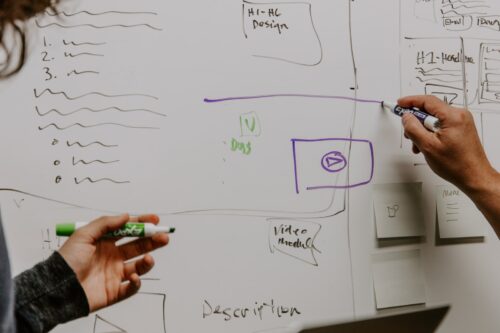
ネガティビティ・バイアスにより、世界がネガティブに映ることが多い一方で、ストレスは私たちの成長や幸せにも貢献しています。
あなたにとって、忘れられない大きな喜びの瞬間は、どんな時でしょうか?
苦難に立ち向かい挑戦し続け、挫折や失敗などを繰り返す。そうしながらも、前を向き諦めずにやり遂げたそんな時に大きな感動が生まれます。
忘れてはならないのは挑戦の過程において、多大なストレスがかかっているということ。ストレスがかかっていたからこそ、大きな感動が生まれます。
逆にストレスなく成し遂げたことは、本質的な感動にはなりません。強く脳に刻まれることもないのです。
ストレス反応は千差万別
さらに、その過程で味わったストレスにより、学びが促進され強くなります。ストレスは間違いなく、私たちを大きく成長させてくれるものです。
しかし、ストレスを成長につなげられる人もいれば、パフォーマンスを下げ成長を鈍らせる人もいます。
ストレス反応のあり方は生まれも育ちも影響し、一人ひとり異なったかたちで表れます。
自分のストレス反応のあり方が、他人にも当てはまるとは考えてはいけません。
大切なのはストレス反応の特徴を学びつつ、自分の場合はどうだろうと考えてみること。私たち自身のストレスに関する理解を深めることです。
そこで、ここからは、ストレス世界の構造を簡単に3つ解説します。
ストレッサーについて
ストレッサーは、ストレス反応導くような情報や刺激のこと。
例えば、「私のストレスの原因は口うるさい上司です!」という人がいるかもしれません。しかし、科学的には、その上司が直接の原因とはなりません。
あくまでストレスの直接の原因は、体の中で繰り広げられるストレス反応です。しかし、口うるさい上司がストレスに関与していることは否定できません。
この上司のように、ストレス反応を導くような情報や刺激をストレッサーと呼びます。
ストレッサーはストレスの間接的な要因です。ストレスを必ず導くというわけではなく、ストレスを引き起こしうる情報や刺激です。
また、ストレッサーは大きく2つに分類されます。
ひとつは外因性ストレッサー、もう一つは急性ストレッサーです。
外因性ストレッサーは、口うるさい上司やけたたましい音などの、外側からやってくるもの。
一方、急性ストレッサーは、例えば上司に怒鳴られたことを思い出すこと。ストレス反応が導かれる内側起点です。
嫌な出来事を思い出すのは、嫌なことをしてきた人が原因ではありません。その記憶を保持し、引き出している自分自身の脳のせいです。
ストレスメディエーターについて
ストレスメディエーターは体内での異変、つまり体内・脳内における内部環境の変化にあたる部分です。簡単に言うと、体のストレス反応そのもの。
ストレスメディエーターが身体の中で合成されることで、私たちはストレスに気づきます。
逆に言うと、たとえストレスメディエーターが身体の中で合成されても、その状態に気づくことが出来なければ、ストレスとしては認識されません。
ストレスメディエーターを認識できたものを、ストレスと呼ぶのです。
また、ストレスメディエーターは、ストレスの直接の原因とも言えます。
ストレス反応が起こらなければ、当然ストレスを感じることもないからです。
そう考えると、ストレスの原因は外の世界にあるわけではなく、実は私たちの体の中にあるとも言えます。
ストレスについて
私たちがストレス反応を認識して、初めてストレスになります。
ささやかなストレス反応に耳を傾けられるようになれば、その段階でストレスを対処することも可能になります。
早めに策を打てば、ストレスは私たちに悪さをすることは少ないです。
逆に、ストレス反応は起きているのにそれに気付けない人は、ストレスの餌食になりやすいということです。
4. ストレスと向き合う方法

最後に、ストレスと向き合う方法についてです。
本書ではさまざまなストレス対策の方法が解説されています。この記事では、その中から2つを紹介します。
ちょっと疲れる運動
まず一つ目は、ちょっと疲れる運動です。
運動の重要性はもう至る所で語り尽くされていますよね。ストレスと向き合う上でも、運動は有効と言えます。
運動することで、脳や隊内での様々な反動が引き起こされ、結果的にストレス反応を低減させる方向に働きます。
また、少し疲れるくらいに運動をしていると、脳にはあまり何かを考えたり思い出したりする余地が残りません。
運動するために脳の回路が買われるので、心理的ストレスに対しては気を紛らわせることができるというわけです。
深呼吸
二つ目の方法は、深呼吸です。これは運動よりも、ずっと簡単なことですね。
呼吸は吸っているときは交感神経が、息を吐いているときは副交感神経が優位になりやすいです。
交感神経は闘争または逃走のための神経系、副交感神経は休息や消化活動促す際に優位に働く神経系です。
心地よく吸気を吸ったら、苦しくない程度までゆっくりと息を吐くそうすることで副交感神経が優位になります。
たとえ1分でも呼吸に集中するだけで、だいぶ落ち着くはずです。
しかし、本当にあたふたしているときは、なかなか実行するのが難しいですよね。
そうならないために、普段から呼吸法を少し練習しておくと良いです。
いざという時に落ち着くための方法として使えるようにしておくことが重要です。
ストレス対策の見方にはどんなものがあるのかしっかりと把握し、いつでも対応できるようにしておきましょう。
今回紹介した「ハッピーストレス」は、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。