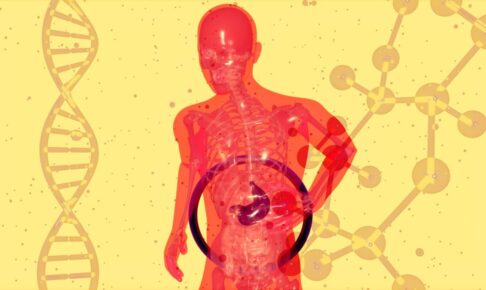フランス語では、蝶々も蛾も同じって知っていましたか?
この記事では、近代言語学の祖と呼ばれるフェルディナン・ド・ソシュールの言語学を解説します。ソシュールはそれまで言語ごとにバラバラに研究されていたものを、言語全体で統一的なルールがあるはずだとして初めて体系化しました。
モノがあるから、それに名前を付けていると、私たちが当たり前だと思える言葉の成り立ちに対して、ソシュールは「言語とは、差異(区別)のシステムである」と言います。いったいどういうことなのか、ざっくり解説していきます!
1. ソシュールの生い立ちと言語学への野心

ソシュールは1857年、 スイスのジュネーブ生まれの言語学者です。ソシュール家は、様々な学者を輩出したきた名家であり、彼は幼い頃から最高の教育環境が揃っていました。ソシュールは、そんな環境を十分に享受し、わずか10歳前後で四カ国語を習得していたそうです。
大学在学中には言語学の論文などを発表し、1880年の23歳の頃にはずでに、パリにある高等研究所で語学の講師をしながら研究に励んでいます。
1891年、34歳でジュネーブ大学の特任教授となり、本格的に言語学の教鞭を振います。順風満帆そうなキャリアですが、当時のジュネーヴ大学はそれほど優秀な大学ではなく、学生の質はそれほど良くなかったそうです。
既存の言語学への問い
ここで、ソシュールの言語学について、簡単に触れていきます。
彼以前の言語学では、ある言語が、過去から現在に向かってどのように変化してきたか?という視点で言語ごとに個別に研究がされていました。
しかしソシュールは、
「過去を知らなくてもみんな言語を使っているのだから、言語を理解するのに歴史は必要ないのでは? 言語それぞれの歴史ではなく、言語全体に流れる統一的なルールがあるはずだ。もっとこう人間と世界のつながりを示すような今までにない新しい言語学はつくり出せないものか…」
という考えに至ります。
ソシュールのこの考えが、言語学の流れを大きく変えることになるのですが、大学のイチ講義で、その後の哲学界に衝撃を与える内容が発表されるとは、当時は誰も想像していませんでした。
ソシュールの想いを残す学生たち
その成果が発表される日、学生たちはいつもどおり、退屈な講義を受けにきただけだったかもしれません。ソシュールは新理論を学生に披露して間もなく、それを世に問うことなく病死してこの世を去ってしまっています。
彼が生涯をかけて追い求めた学問の成果を、このまま埋もれさせてしまっていいのか。ソシュールの授業に参加した学生たちは奮起し、その日の講義内容を、ソシュールの死後に講義を受けた学生らが「一般言語学講義」としてまとめて出版しました。
これにより、彼はその死後に、近代言語学の祖として一躍有名になったのです。
2. ラングとパロール

ここからは、ソシュールの言語学について、もう少し深掘りしていきます。
ソシュールは、歴史を考慮しないその時点の言語ルールのことを“共時態”と呼び、さらにある共時態が次の共時態へと変わっていく状態のことを“通時態”とし、言語学は出発点として、共時態について研究すべきだと主張しました。
そのうえで、現時点で使用されている言語という概念について徹底的に考え、二つの側面に分けて考察します。一つは、“パロール”。これは個別の“発話行為”そのものを指します。私たちが言葉を発するとき、その行為をパロールと理解してよいです。
もう一つは“ラング”。これはある言語における文法体系や規則のこと。日本語の話者同士がコミュニケーションができるのは、一定のルールがあるからでよね。それが、ラングです。
そして、パロールとラングを掛け合わせたものが、その言語の全体像になりますが、ソシュールはその全体像を“ランガージュ”と呼びました。
ソシュールはそのように分別したうえで、ラングについて研究することが、言語学であると捉えました。
3. 言語名称目録観に対する違和感

ソシュール以前の言語学者たちは「言語名称目録観」を基盤に言語を考えていました。 これは、あるものに対して一つ一つラベルが貼るように、ものの名前が決まっているという考え方です。
例えば、りんごという物質には人間が存在する以前から、りんごという名前が設定されていたという考えです。いま考えればすぐに違和感に感じるかもしれませんが、当時はこの考え方が主流でした。
しかし、これでは言語によって対象の切り取り方が異なることを、説明できません。
日本語とフランス語の名前の違い
例えば、日本語では、蝶と蛾は別の昆虫だと識別されます。綺麗なアゲハチョウを見て「蛾だ」という日本人はまずいないですよね。
一方で、フランス語においては、蝶も蛾もどちらも同じ「papillon(パピヨン)」と表現します。 フランスでは蝶も蛾も、同じpapillonという昆虫です。
違う例として、河川敷に落ちている石ころを考えてみましょう。あなたはそれらの石一つ一つを区別して、名前をつけているでしょうか?よほど思い入れのある石でない限り、同じ“石”と呼びますよね。
このように、その言語において、区別する必要があるものは別の名前がついており、区別する/しないは言語によって異なります。もし、言語名称目録観により、存在に最初から名前がついているとしたら、矛盾しています。
4. 蝶でないものとしての蛾

ソシュールは言語による命名の矛盾に対して、「個別の存在に意味は存在しない。それらは隣り合うものとの“対立関係”によってはじめて成立する」という考えに至りました。
例えば、それぞれの存在にもともと名前があって、それらが集合している状態は、以下のように表すことできます。
箱の中にあらゆる物体が、ぎっしり詰まっている状態があるとします。仮にこの状態から、Bという名前のものを抜き取ったとすると、抜き取られたBのあった言語空間を埋めるものは何もありませんよね。
この時、箱からはBという名称と一緒に、Bという物質も消えてしまいます。これが、ソシュール以前の言語感だと言えます。
対立関係によって成り立つ言葉
一方でソシュールの考えでは、例えば、青っぽい色の言葉の集合を取り出し、そこから青色と水色の中間くらいのオリエンタルブルー色を抜き出したら、どのようなことが起こるでしょうか?
その場合、隣接していた青色と水色がオリエンタルブルー色の領域を埋めることで、何もない空間が補填されます。オリエンタルブルー色という言葉がこの世からなくなっても、その両隣にある言語に対応した色の呼び名は補填されるのです。
つまり、蝶がいるから、蝶でないものとしての蛾がいるのであり、逆も然り。どちらかがなければ、両者はフランス語でいうところのパピヨンでしかなくなってしまうという対立関係にあるのです。
5. 言語は差異のシステム

「言語とは、差異(区別)のシステムである」
これがソシュールの主張です。
リンゴがまずあるのではなく、赤い何かを他の何かと区別したいから、リンゴという名前を付けられたという順序です。
私たちは河川敷の石たちに対して、区別する価値はないと判断し、区別していないのです。
もし仮に、私たちと同じ食文化を持たない惑星の宇宙人いたとしたら、リンゴもみかんもメロンも、区別する必要のない”有機物の塊”に過ぎないかもしれません。
これと同じように、異なる文化圏においては、「言語体系の違い = 区別体系の違い」と言えます。
文化によって異なる区別の基準
もう少しだけ、例をみてみましょう。
日本語では、姉と妹を明確に区別していますが、英語圏の人たちはsisterという一つの言葉でくべせずに表現しますよね。彼らの価値観では、sisterの対象が年上か年下かはさほど問題ではないということです。
フランス語圏では犬と狸を区別せずに、「chien」という一つの言葉で表現したり、逆に英語圏の人たちは白いうさぎと茶色いうさぎを厳密に別の言葉に区別したりしています。
それぞれの文化圏で染み付いた常識があり、他の文化圏の人にとって、「いや、それはどうでもいいでしょ」と思えるようなことを、私たちが区別する反面、彼らも私たちがどうでもいいと思えるものを言葉として区別しているのです。
このように細かく区別すると、すべてのものは最終的には原子や陽子、中性子まで分解されると思っているが、それすらも私たちが勝手に区別したものだと気付かされます。
例えば、家族や国家という区切り方もまったく異なった区切り方をしてもよかったはずです。そして、区切り方を変えれば、今までとは違う世界が姿を現わすことになります。
6. イヌという言葉自体には何の意味もない

仮に異世界の怪物からみた私たちの世界は、国家や地域で人を区別するでしょうか?
ましてやネコやゾウ、木々と人を別モノだと口別するでしょうか?
リンゴという物質は、リンゴがこの世にあるから存在しているのではなく、リンゴをリンゴとして区別する価値観があるからこそ、そこに存在している。
リンゴを区別する人がいて、はじめてリンゴが存在するのであり、区別する人がいなければリンゴは存在しないことになります。
あなたが見ている世界は、あなた特有の価値観で切り出された世界であり、その世界に存在するものすべては、あなた特有の価値で切り出された存在にすぎないのです。
またソシュールは、言語が音として成り立つ側面を“シニフィアン”。言語が意味を持つ側面を“シニフィエ”と呼び、この両者が結びつくことで“記号(シーニュ)”が生まれると考えました。
つまり、「ちょ う ちょ」という発音自体をシニフィアン、「ひらひらと舞う、カラフルな昆虫」という意味をシニフィエとして、この二つが合わさることで、“蝶々”という言葉が完成するのです。
そして、何よりも重要なのが、シニフィアンとシニフィエの両者が結びつくことには、なんの必然性もないということ。偶然その音と意味が結びついただけ。
蝶々が“イヌ”と発音される存在だったとしても、その言葉や発音自体には何の意味もありません。この考え方を「言語の恣意性」と言います。
ここまで解説したとおり、ソシュールは、
「言語の秩序を細かく分類していくことで、最初から名前が付いた存在はなく、ある言語のルールの中で偶発的にその結びつきが作られ、それらは他の言葉との対立関係の中でのみ存在している。」
と結論付けました。そして、この言語論的転回は、後の言語学だけでなく、 実存主義の後に活発になる構造主義に大きな影響を与えたのです。