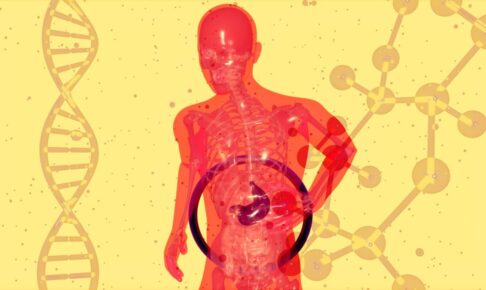私が本書を通じて伝えたいのは、生命の原理や原則を客観的に理解した上で、それに抗うために主観的な一生を生かして行動できるということです。
ーー高橋祥子
この記事では、生命科学者である高橋祥子さんの「ビジネスと人生の見え方が一変する 生命科学的思考」という本を紹介します。本書は、ビジネスや人生のヒントを生命の原理原則から知りたいという方におすすめです。一見すると非合理的に思えるようなことも、生命科学的には説明が付きます。

高橋祥子さん
死・感情・ガンの発症といった、人間の遺伝子に組み込まれたものには合理的な理由があり、人間に備わる主観こそが、そうした遺伝子に歯向かう力が得られる。そして、それら生命の原理原則は、人生やビジネスも役立つと著者は言います。
いったいどういうことなのか。さっそく中身をみていきましょう!
1. 生命に共通する原則

まずは生命に共通する原則について、本書から3つのポイントを解説していきます。
なぜ私たちは死ぬのか
死や悲しみ、苦しみ、争いなど、私たちの世界は非効率なことが溢れていますよね。これらの原因を知るためには、全てに関係する生命の原理原則を認識する必要があります。その原則とは、“すべての生命は個体として生き残り、種が反映するために行動する”ということです。
例えば、食欲や睡眠欲は生き残るため、性欲は種として繁栄していくために必要不可欠です。そのため、この仕組み自体を否定した行動を起こしても意味がなく、不具合が生じるだけです。日常生活を送る上で根源的な欲求をコントロールしたい場合は、それを否定するのではなく、性質を理解してうまく付き合っていく必要があります。
生命原則を理解する上では、生命はとても非効率な存在だということを、まずはしっかり認識しましょう。その中でも最も非効率と思えるのが“死”です。死は苦労して作り出した命をわざわざ壊すという、非効率で非合理的にも思える行為。なぜ、死は存在するのでしょうか?
「不死」の定義
この問いに答える前に、「不死」の定義を考えてみましょう。例えば、魂を機械に移植したアンドロイドのような“機械化人”が存在したら、その人は不死と言えるでしょうか?
生物学的には不死とは言えないと、著者は言います。なぜなら、体が機械になった状態では、それ以前と同じ意識や感覚で生きていた時と“連続性”を持って、物事を考えられないからです。体の感覚が、意識に与えている影響は思っている以上に大きいです。
例えば、夏目漱石の意識をロボットに移すことができたとします。皮膚で感じるそよ風の暖かさ、耳で感じる静けさ、鼻で感じる匂いといった身体的な感覚が急激に変化したとすれば、「I love you」を「月が綺麗ですね」と、訳せたでしょうか?
機械の身体になった時、以前の体を持っていた時と同じ意識や思考を維持できる保証はありません。生物学的な観点から見れば同じDNA配列を持つ身体を、連続性を持って維持すること。これが不死の定義となります。機械もしくは別の生命体に意識を移植した時点で、遺伝子の連続性がなくなります。
それは生物個体としては死であり、新たな個体として生きるということになります。また、たとえ意識を新たな個体に移植できるとしても、身体性に由来する周辺情報と脳が関係していることを考えると、体が異なるということは新たな別の個体と捉えられます。死は連続性の喪失であり、裏を返せば死を新しく生が生まれ変わっていく仕組みと言えるのです。
死の目的は、非連続性の創出
つまり、“非連続性の創出”こそが、死の存在理由です。そして、死がなぜ必要なのかというと、生命が生きる環境が変化するからです。生命の原理原則では、個体を取り巻く外界の環境が常に変化する前提で作られています。
例えば、地球の気温が現在のように温暖になったのは、ここ1万年くらいであり、それ以前は氷河期時代のように気温が低い時もあれば、今より気温が高かった時もありました。環境の変化のスピードは大きく、一つ一つの個体が連続性を持ったまま適用するには限界があります。そこで、生命は新しい個体を作り続け、来るべき環境変化に備えようとするのです。
特に人類のような有性生殖を行う生命は、子供を作る時に遺伝子の一部を変えることで、親とは異なる遺伝子を持つようになります。そして新しい生命が活動していくためには、古い生命と入れ変わるための“死”が必要というわけです。
2. 感情にも、ガンにも理由がある

なぜ感情があるのか
死と共に不自由なものに、感情があります。感情は人間関係を築く上で必要不可欠な一方で、トラブルの原因にもなります。ストレスや不安を感じやすい、あるいは感情のコントロールができず、ついつい他人に強く当たってしまう人もいるかと思います。ストレスを感じることなく、みんな穏やかに過ごすことができればと思う人もいるでしょう。
しかし、残念ながら現実にはこうした感情とうまく付き合っていくしかありません。なぜなら、各々が持つ感情の差異と遺伝子を結びつけることが、生命の生存戦略上有利だからです。
1973年にノーベル生理学医学賞を受賞したニコ・ティンバーゲンは、“何を目的として行動が引き起こされるのか”という直接的要因だけでなく、“その行動が生物学的にどのように獲得され、子孫を残す上で有利に働いたか”という進化要因を考える必要があると指摘しました。個人が持つ感情についても、それが生物学的にどんな意味を持つのかを考えることで、より深く理解することができます。
例えば、他人に対して怒りを覚えるのは、自分の敵に対応するためです。孤独を感じるのは、集団で生活することで生き延びてきた人類が、一人で生きることを避けるための感情です。こうした感情は、生きていく上での危険を察知し、その危険から離れたり、排除したりするために必要な機能として存在します。
感情を抱いたときは自分が感じているというよりも、遺伝子に搭載された機能が正常に働いていると、客観視するといいかもしれません。
こうしたメカニズムやその意味を知っておくことで、非効率で面倒くさいものと思えるネガティブな感情とも向き合いやすくなります。また、身を守るために遺伝子に搭載されている基本的な機能だからといって、現代の環境に感情が最適化されているとは限りません。
本能的な感情の機能が、今の環境でも本当に必要なのかどうかと考えてみると、感情と折り合いが付きやすくなるでしょう。
なぜガンは進化の過程でなくならなかったのか
細胞が分裂するとき、それに先立ってDNAが2つにコピーされます。この時ほぼ正確にコピーされますが、コピーしなければならない文字列が約30億にのぼるため、1億~100億分の1の確率でコピーミスが起きます。このミスが細胞増殖に関わる遺伝子で起き、細胞が増えなくてもいいところで増え続けると、やがて臓器の機能に支障をきたすほどの大きさに成長します。これがガンです。
DNAのコピーミスによって生じるガン細胞は、1日に5,000個にも及ぶと推定されています。そのほとんどは免疫によって破壊されますが、その中でも生き延びたものが成長を続けると、大きな細胞集団となりガンと診断されるようになります。
では、DNAのコピーミスはなぜ起きてしまうのでしょうか?ミスを修復する仕組みをつくり、絶対にガンが発生しないようにすることはできなかったのでしょうか?
ガンは今でも進化の可能性を秘めている証拠
しかし、コピーミスは進化のために、どうしても生じてしまうものです。進化は生命が長い歴史の中で常に変化し続ける環境で、生き延びるための方法です。常に一定の頻度でDNAが変化することで、異なる遺伝子、異なる性質のタンパク質を作り、そして異なる生物を作る。現在6,000の生物種があり、地球のあらゆる場所に生物が存在するのも、常にDNAのコピーミスを含む変異が起こり続けてきた結果です。
例えば、ホタルが発光するようになったのも、元は他の遺伝子が進化の過程でコピーミスにより、何度も重複を起こし、発光する機能を持ったためであることが、ゲノム解析から分かっています。私たち人類が常にガンに脅かされているのは、今でも進化の可能性を秘めている証拠なのかもしれません。
遺伝子のコピーミスはガン細胞になることもあれば、新しい進化のきっかけにもなり得るのです。生命はまだ見ぬ未来への進化のために、DNAのコピーミスというガンを引き起こしてしまう可能性のある性質を、種の存続のために命がけで持ち続けているのです。
3. 生命原則に抗い自由に生きる

ここからは、“生命の原理原則に抗い自由に生きる”ことについて、本書から2つのポイントを解説していきます。
主観こそが創造主に歯向かう鍵
生物としての仕組みを俯瞰的に見てしまうと、自分も長い生命の歴史の一部に過ぎないと、悪い意味で達観してしまう人もいるかもしれません。しかし、人間は主観的な意思を生かして行動できる数少ない生物であり、そこに希望があると著者は言います。
主観といっても、本能のままに非客観的・情緒的に行動しよう!ということではありません。本書では「主観」という言葉を、遺伝子として規定されている生物としての共通した機能ではなく、個人が特有に持つ遺伝子に歯向かう意思という意味で用いています。
私たちは遺伝子に従った生命活動を無意識に実行していますが、遺伝子に歯向かう自由意思が存在すると考えることで、実際の行動自体を変えられる余地があります。この遺伝子に歯向かう意思が存在するなら、それはどこに存在し、どのような性質があるのでしょうか?
主観的に臨む
唐突ですが、世の中にはさまざまな課題があります。課題というと、企業や社会レベルの大きなものもあれば、個人レベルの悩みもありますよね。世界レベルでは飢餓や貧困、気候変動に代表される環境問題、日本レベルでは超高齢化社会、個人レベルでは今後のキャリアや人間関係の問題、健康問題などです。
これらの課題は一見、元からそこに横たわっていて、自然に発生したかのように思えますが、実際はそうではありません。そのほとんどは、それが解決された状態を私たちが主観的に臨むことで、初めて課題として存在します。つまり、自ら選んで課題を設定できること自体が、極めて自由かつ主体的な性質を持つことになります。
著者は毎月1つずつNPO法人や社会活動団体に寄付を行っているそうですが、その中には子どもの虐待を防止する活動、貧困救う食堂を運営する活動、沖縄県でサンゴの養殖を行う活動など、それぞれの団体の方々が設定する課題は多岐にわたっています。それらの課題1つ1つは、こういう未来を描きたいから、好きだからといった主観的な意思に基づいており、遺伝子によって規定されているだけのものではありません。
つまり、世の中にある様々な課題は主観的な意思が作り上げており、逆に言えば課題を見つめることで自身の意志が見えてくるのです。そこから見えてきた自身の主観的な意思を認識することが、課題解決への推進力となると著者は言います。私たちの行動が生命原則に基づいていると知る一方で、自身の意思に基づいた行動を取ることが、生命原則へ抗う力となるのです。
主観が見つからなければカオスに身を置け
しかし、自分の意志を持って行動を起こすほどの目標がない、やりたいことが見つからないという人もいるでしょう。
主観的な意思を持ちたいけど、どうすればいいのかわからない人に対する著者のアドバイスは、カオスな環境に身をおくべきということです。カオス(混沌)は、秩序がなく予測が不可能な環境のことです。予測できない環境の中で、理不尽と思えることに直面した時にこそ、自分が何を求めているのかについての認識が深まり、初めて理想とする世界を決めることができます。
例えば、著者が周囲の起業家に聞いた話によると、東日本大震災で感じた自分の非力さをきっかけに起業した、難病で生死の境をさまよった経験から人生をかけてこの仕事をやり遂げたいと改めて気づいた、といった人があるそうです。
これらはカオスな経験としては分かりやすいですが、もう少し現実的でかつ個人の意思で身を置くことができるカオスの例として、達成できるかどうか分からないほど難しいことや、難しい環境に挑戦することを著者は勧めています。似たような話として、「人生は攻略できる」という本でも、中程度の逆境がある方が幸せになれると書かれています。
“なぜ”という言葉の重要性
規則正しく流れ、どこにたどり着くかわかっている清流であれば、意思を持たず流れに身をまかせても何の問題もないでしょう。しかし、どこへ行き着くかもわからないような大河に入るのであれば、羅針盤は必要不可欠になります。カオスな環境で他力本願では、行きたいところへ行きません。自然と自分だけの羅針盤、つまり“主観”を持てるようになります。
- なぜ予測できない方向に向かってしまうのか
- なぜこんな理不尽な目に合わないといけないのか
- なぜ世の中はこうなっているのか
など、疑問が生まれるようになります。カオスであればあるほど、疑問は生まれやすくなり、主観につながっていくのです。
“なぜ”という言葉から始まる疑問は重要だと著者は考えます。 5W1HのうちWの5つは、客観的な視点から疑問が生じます。一方で、“なぜ”にあたる“Why”だけが、自分に関わる主観的なものです。なぜから始まる疑問は社会ではなく、自分の主観に紐づいています。
例えば、超高齢化社会だということは客観的に話せますが、「なぜ超高齢化社会になっているのか?」と感じた瞬間に主観的な考え方が生まれます。ある人は、超高齢化社会にならないためにはどうすればいいか、超高齢化社会で起こりうる問題を解決したいと考えるかもしれません。
このように、“なぜ”が発生した瞬間に、その問いに対する思考に主観が生まれ、何を目指したいのか、そのために自分はどう行動すべきか、という自分軸が発生します。やりたいことが見つからない人も、いま自分が置かれている環境が辛いという人も、なぜの問いを積み重ねていくことで能動的に信念を固めていけるようになります。
なぜ自分は今の道を進んでいるのか、なぜ自分は今の環境が辛いのか、などのなぜを積み重ねて生まれてくる主観は、他の誰にも否定されない他の何者にも代替できない貴重な命題となり、それがカオスな世界を突き進む糧になるのです。
今回紹介した、高橋祥子さんの「ビジネスと人生の見え方が一変する 生命科学的思考」については、まだまだ紹介できていない部分が多いです。もっと生命科学と生き方について知りたいと思った方は、ぜひ本書を手にとって読んでみてください。