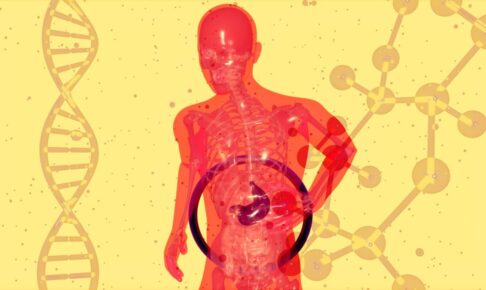現代のアートプロジェクトや政治や社会問題と芸術を語る上で、避けて通れない芸術家がいます。その名は、ヨーゼフ・ボイス。戦後において、社会的・政治的な問題に芸術が積極的に関与していく必要性を説いた人物です。ボイスは「社会彫刻」や「拡張された芸術概念」などの独自の哲学を展開し、ドローイングや彫刻造形のみならず、レクチャーや、対話集会、アクションなど表現は多岐にわたり、政治経済、環境問題についても積極的に介入しました。人間ひとりひとりが参与することでより良い社会をつくりあげ、自覚を持ち行動する人は「誰もが芸術家」であると説きます。この記事では、そんなボイスが活躍した時代背景や、彼の作品の特徴を解説していきます!
1. 動物や植物を愛する幼少期と第二次大戦

ヨーゼフ・ボイスは1921年、ドイツ西部の都市・クレーフェルトの質素な家庭に生まれました。その年にオランダ国境近くの田園都市・クレーフェに移り、そこで幼少期を過ごします。幼い頃からドローイングの才能のほか、ピアノやチェロなど楽器を弾く才能も秀でていたボイスは、家の近くに住むアヒレス・モルトガットのアトリエを頻繁に訪ねていました。そうした環境下で、芸術に接する機会もあったほか、北欧の歴史や神話、自然科学など多くのことに興味を持ちます。しかし少年ボイスは、芸術家になることは考えておらず、医学の道を進もうと考えていたそうです。1933年5月、ナチスが学校の中庭で焚書をはじめたときに、ボイスは燃えさかる大量の本の山から生物学者カール・フォン・リンネの「自然の体系」を拾い上げたという逸話もあります。
1936年、10歳から18歳の青少年全員のヒトラー・ユーゲントへの加入が義務づけられ、15歳のボイスも加入。この頃、ヴィルヘルム・レームブルックという彫刻家から影響を受け、彫刻家になることを決意します。一方で1941年、ボイスはドイツ空軍への入隊を志願し、ハインツ・ジールマン(戦後西ドイツで野生動物のドキュメンタリー映画作家として有名になった人物)の下で、軍の航空無線の訓練を受けます。1943年には、ケニグラーツに駐屯していたJu 87(シュトゥーカ)急降下爆撃機に無線オペレーターとして搭乗、東部戦線で実際に戦っています。ちなみに、戦下でボイスが描き溜めていたドローイングやスケッチは現在も保存されています。
1944年、ボイスはウクライナ近くのクリミア上空で、ソ連軍に撃墜されてしまいます。ボイスの記憶によれば、現地の遊牧民であるタタール部族が、墜落して意識のないボイスの体に脂肪を塗り、フェルトで体を覆い体熱が下がるのを防ぎ、生死の淵から生還できたそう。記憶の中で、覚えているのは「水」と話したことや、テントで食べたチーズや肉、ミルクの味。ボイスは回復後、タタール部族と良好な関係を築き、部族に加わらないかと説得されたこともあると、のちに何度も語っていますが、当時クリミアにタタールの集落はなかったそうです。しかし、ボイスにとってタタール部族とのエピソードは、彼の芸術の起源となったことは疑う余地はなく、看護の際に使われた脂肪やフェルトといったモチーフは、作品の表現にダイレクトに反映されていくこととなります。
2. デュッセルドルフ美術大学での出来事

終戦後の1946年、ボイスはデュッセルドルフ美術大学で芸術を本格的に学び始めます。1947年には、前衛芸術家のエワルド・マタレーのクラスに参加。彼は、戦前にナチスによって退廃芸術の烙印を押され、弾圧された芸術家の一人でした。マタレーや、この頃出会ったルドルフ・シュタイナーの人智学は、ボイスの哲学である「社会彫刻」など需要な概念の基盤となりました。また、再び自然科学への関心を高め、ハインツ・ジールマンと1947〜49年まで自然・野生動物に関する研究を行いました。
1951年、ボイスは引き続きマタレーに師事し、マスタークラスへ入室。この頃は、ガリレオ・ガリレイや、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、社会的に強い影響力を持っていた芸術家や科学者たちから刺激を受け、ボイスにとっての社会芸術の源となりました。1953年にマスタークラスを卒業した後は、墓石制作や家具などさまざまな工芸仕事をして、わずかな収入で生活を始めることに。伝統的でない新たな素材や、自然現象や哲学の表現方法を探求しますが、1956年には、自己の芸術に対する疑問や生活の貧困のため、ボイスは重度のうつ病になってしまいます。彼は、1950年代を通じて、貧困と戦争時のトラウマと何度も戦っていました。
1961年、40歳で母校の教授となったボイスは、生徒とともに様々なパフォーマンスを開始。そんな矢先、アドルフ・ヒトラーの暗殺計画から20周年を迎えた新しい芸術祭典の一環として行ったパフォーマンスでは、パフォーマンスを生徒たちが中断したため、ボイスは生徒の1人に殴りかかる事件を起こします。当時の事件写真には、鼻から血を流して腕を上げているボイスの姿が多くのメディアで取り上げられました。また、この芸術祭典でボイスは独自のCV(履歴書)である「ライフ・コース」を発表。そのCVは、比喩的かつ神秘的な記述で歴史的な事件と、自身の芸術人生を混合させた架空のCVでした。これによって、ボイスの過去のさまざまな出来事、特に先に紹介したタタール民族との話などが、真実なのか虚構なのか、今でも定かではありません。
さらに1960年代後半、ボイスは自身のクラスの開講にあたり、入りたい者すべてに対し開かれるべきだと主張し、アカデミーの入学要件を廃止する案を発表。この国家への反発ともとれる政策は、アカデミー当局との間で大きな制度的摩擦を生み、1972年にボイスは教職を解雇させられることになります。アカデミーとの4年間に渡る裁判を経て和解が成立しますが、この出来事をきっかけに、ボイスは自由国際大学の構想を固めていきます。なお、彼の授業を受けた学生の中には、ゲルハルト・リヒター、ジグマー・ポルケ、アンゼルム・キーファーなど、その後のドイツ美術を代表する作家たちが多く在籍していました。
3. フルクサスと社会彫刻の実践

1962年、ボイスは短期的に、芸術領域の境界線を越え、美術の外側での日常における創造の実践を目標とした“フルクサス”のメンバーとなり、その後この運動で活躍するナム・ジュン・パイクらと親交を持つようになります。フルクサスは、第一次世界大戦時に発生したダダイズムの直接的な影響を受けていましたが、1964年にボイスはテレビ放送された自身のアクション作品「マルセル・デュシャンの沈黙は過大評価されている」で、ダダイズムの代表格であるデュシャンを強く批判。既存の芸術の域を超えて、社会や大衆に向かって原始的で直観的、感性的でダイレクトに訴える芸術の実践をしていたボイスに対して、デュシャンのことを大衆とは遠く離れた場所で芸術を発表し、社会と芸術を乖離させたと主張しました。ボイスは、芸術を「誰もが生きるために役立つ技術」と考えていたのです。
フルクサスを離れた後、ボイスは「芸術が社会に対し何をなしうるか」という命題のもと、多くのオブジェを制作したり、パフォーマンスを演じたりするようになります。1965年、ボイスはギャラリーでの初個展の際に、頭部に蜂蜜を塗り、 その上に金箔を貼り、鉄の厚底の靴を履いて登場。観覧客を外に追い出し、死んだ野うさぎを腕に抱き、そのうさぎに絵画を説明。鑑賞者はガラス越しに、その様子をただ眺めるといったパフォーマンス《死んだうさぎに絵を説明する方法(1965)》を展開しました。鑑賞者は当然、ボイスがなぜ変な格好をしているか、何を説明しているのかを理解することはできません。このパフォーマンスでボイスは、絵画をよく理解するには饒舌な説明を聞くのではなく、絵そのものをよく見ることのみということを体現。このパフォーマンスはボイスにとって、人間が未来の世界や社会を創造性によって造形していく独自の概念「社会彫刻」の重要な分岐点となりました。ちなみに、ボイスにとって蜂蜜を作るミツバチの生態系は、暖かさと兄弟愛に包まれた理想的な社会を表し、金は錬金術を表し、鉄は火星を表しているそうです。
4. 熱としての芸術、オルタナティブとしてのパフォーマンス

《グランドピアノのための等質浸潤 (1966)》
ボイスの芸術にとって、変化や生命を意味する“熱”は重要な要素です。伝統的な彫刻は生命の証拠である熱エネルギーを有していないし、形が変わっていくこともない。ボイスは彫刻を有機的なものにするため、熱によって形が変化したり、熱を保持したりする機能がある素材を好んで用いました。例えば、1966年に制作した《グランドピアノのための等質浸潤》では、“フェルト彫刻”という新たなジャンルを打ち立てたほか、《フェルトスーツ (1970)》や《脂肪の椅子 (1964)》などで、作品にフェルトや脂肪といったタタール部族とのエピソードに由来する素材が繰り返し使われています。また、フェルトは熱エネルギーを保持するもののメタファー(比喩)でもあります。
変わったパフォーマンスとしては、ベルリンのルネ・ブロック画廊の地下では、大きなフェルト製の毛布を敷いて、その中にボイス自身がくるまる《チーフ (1964)》という作品を展開。毛布の両端には2頭の死んだ山羊が、その周りには胴棒、フェルト、脂肪が置かれていました。毛布の中でボイスはマイクロフォンを手にし、観客が見ている中で8時間もマイクロフォンに向かって何かつぶやいていたそうです。その他にも1974年には、《私はアメリカが好き、アメリカも私が好き》というパフォーマンスをニューヨークのレネ・ブロック画廊で実施。これは、ボイスが画廊の中でコヨーテと1週間一緒に暮らし、実際のアメリカ人とは接触しないというものでした。アメリカ先住民の間では神聖視され、後に白人によって迫害されたコヨーテを、ボイスは「真のアメリカの姿」ととらえ、コヨーテとのみとコミュニケーションをとろうとしたこの作品は、先住民やその文化の迫害の延長に存在する、近代以降のアメリカ社会を暗に批判したものでした。

《チーフ (1964)》

《私はアメリカが好き、アメリカも私が好き (1974)》

《7000本の樫の木 (1982)》
戦後の高度成長がピークを迎え、環境汚染が問題視されはじめると、ボイスは緑の党の設立に関わるなど、エコロジー運動にも参加します。そして、晩年の大規模なプロジェクトとして、《7000本の樫の木 (1982)》を開始。これは樫の木をカッセル市内に植樹するもので、その対として植樹された樫の木の傍らには、玄武岩が埋められました。成長する樫の木は地球上の有機物(生)を、形を変えることのない玄武岩は無機物(死)を象徴しており、二つの要素が存在することで、世界は構成されていることを暗示しています。このプロジェクトの実現に奔走しながら、ボイスは86年、この世を去ります。
既存の制度やイデオロギーに規定されている人々の惰性的な日常に揺さぶりをかけ、個人が自ら思考し、判断することを目的としていたボイスの芸術活動。それは、戦争という最悪の悲劇を経てもなお、未来を拓く人間の可能性にかけた、人々や社会への挑発と終わりない闘いでした。彼の残した“熱”は冷めることなく、今日も後世の芸術家たちに影響を与え続けています。