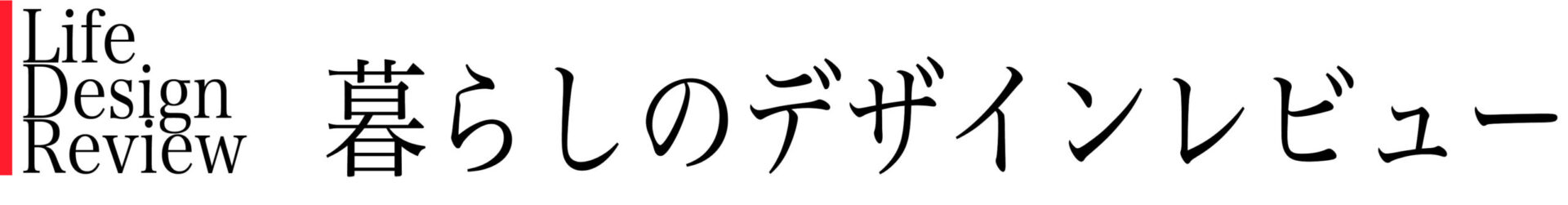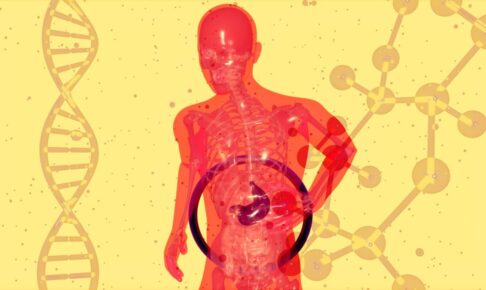この記事は、脳科学者の中野信子さんが書かれた、「世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた」の紹介、後編です。
前編では、
- 自分を過小評価しない
- 90点以上狙えることに注力する
- 30点以下しかできないことはしない
といった、世界に通用する頭のいい人たちの特徴を紹介しました。ここで、「でも、これって頭のいい人たちだけに必要な特徴じゃないの?」といった疑問が湧いてきますよね。
日本人は何でも一人でやろうとする、ゼネラリスト傾向の人が多いです。その環境で育つと、これらの特徴は極端に感じるかもしれません。しかし、これらの特徴によって、周りを自分のペースに巻き込んでいく力を持っている人が、結果として世界で活躍しているのも事実です。
後編では、世界の頭のいい人たちの心がけや行動を具体的に紹介していきます。私たちが日本人的に常識と思っていたことを見直すきっかけにもなるはずです!
1. 世界の頭のいい人は、空気を読まない

世界で通用する頭のいい人は、ちょっと非常識だったり、一見大人げないことをしたりするそうです。しかも著者は、この特性は簡単なコツやテクニックを少し練習するだけで、誰でも習得できると言います。要するに、「頭のいい人の行動 = 地頭がいいからできる」ではないのです。これを機に、少し趣向を変えてみるのもよいのではないでしょうか?
まず、 “空気を読まないこと = 周囲に気を使えない、わがまま”といったマイナスのイメージは、捨てた方がいいかもしれません。空気を読まずに嫌なことを他人に頼むことで、周囲に迷惑をかけたり不快な思いをさせるとは限りません。結果として、協力してくれた人もいい思いをすれば、むしろプラスに働きます。
得意なことだけを貫くことは自己中心的に思えますが、良い結果を残すためには大事な要素です。一方で、自分が得意なことを頼まれたときには快く引き受ける。そうすれば、自然と評価や信頼が獲得できそうだと思えませんか? それでも得意なこと以外を頼むのは気が引けて空気を読んでしまいそう…。という方は、周りから助けてもらえるのがうまい人になりましょう。
2. 周りから助けてもらえるテクニック

ここからは、周りから助けてもらえるテクニックを解説していきます。まずは、嫌な仕事を他人に振る方法について。自分が嫌なら他人も嫌だろう…と思うのは、気が早いようです。
一見つまらなそうなことでも、得意な人や楽しめる人はいます。上手に褒めながら頼めば、自分に味方をしてくる人はきっといるはず。自分の苦手な部分を周囲の人たちにフォローしてもらうためには、褒め上手になる必要があります。
ただし、当たり前ですが、単に褒めるだけではダメです。手当たり次第に褒めていると、この人は自分のことをバカにしているのでは?と思われる可能性すらあります。嬉しい反面、これ本当に本心なのかな?と、疑った経験がある人も多いのではないでしょうか?
重要なのは、手伝ってくれた人にちゃんとお礼をすることです。雑用やちょっとしたことでも、お礼を忘れてはいけません。お礼をすることで、周囲の人は気分が良くになりますし、自らもお互いに助け合うことを楽しんで生活することができます。もちろん、お礼は相手が喜ぶことをしましょう。
- プレゼントを贈る
- 美味しいものをおごる
- 能力が高いことを周囲にアピールしてあげる
など、何を喜ぶかは相手によって様々なはず。無理に見栄を張ったお礼は必要ありません。頼んだことに見合うようなレベルでお礼を考えましょう。
大事なことは、相手を知りその人に合わせたお礼を用意することです。いきなりは難しくても、普段から人を観察していれば、何が喜ばれるか少しずつ分かるようになるはず。テクニックと言いながら、当たり前のことを書いてしまった気がしますが、頭のいい人ほど上手に相手を褒めながら、自分の弱点を補ってもらっているということです。
3. 自分に適度なストレスを与える
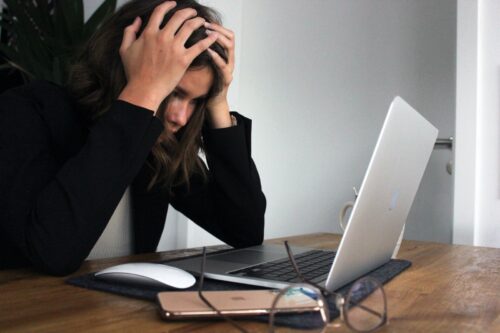
頭のいい人が心がけていることの一つに、“自分に適度なストレスを与える”ということがあります。ストレスって体にも心にも良くないし、遠ざけた方がいいんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、ストレスは人間にとって必要不可欠なものです。
もちろん、過度なストレスは害になります。しかし、ある程度であれば、私たちのパフォーマンスを最大限に高めてくれます。世界の頭の良い人は、自分で自分を追い込むことで、成果を残しています。
例えば、私たちは日常の中で、
- 明日までに課題を終わらせないといけない
- 朝までにプレゼンの資料を完成させなければならない
- テスト勉強が追いつかないから徹夜をする
など、その前日や夜に、ものすごい集中力で作業が進めた経験はありませんか?
極端にストレスがなさすぎる場合や、逆にものすごいプレッシャーがかかり、ストレスにさらされている場合、記憶や知覚のパフォーマンスが低下します。逆に、適度なストレスは学習パフォーマンスを最高レベルに高めてくれます。一時的な感情によるストレスと知覚や記憶のパフォーマンスとの間には、上述のような心理学の基本法則があり、“ヤーキーズ・ドッドソンの法則”と呼ばれているそうです。
4. 集中力を身につけない

もう一つ、世界の頭のいい人に近づくために私たちが心がけるべきことを紹介します。それは、集中力を身につけないことです。多くの人は集中力が続かないことを悩んだり、集中力を身につけるにはどうすればいいかに興味がありますよね?それなのに、集中力を身につけないとはどういうことなのか。
著者は、まず “集中力を身につける” という発想を、捨ててほしいと言います。本来、脳は集中できる環境を作ってあげると、勝手に集中するようにできています。つまり、集中力を身につけるために、効果があるかもわからないような努力をするより、脳が集中しやすい環境作りをするほうが、ずっと簡単で効果的ということです。
事実、著者は自他共に認めるほど、かなり目移りしがちな性格だそうです。しかし、高校時代はお母さんにあまり勉強すると頭がおかしくなるからやめなさい!と、勉強のしすぎを怒られるほどに集中して勉強していたそうです。
これは、著者に集中力備わっているからできたのではないと言います。集中するためのお膳立てがうまくいっていただけ。つまり大抵の人は集中できる環境を、自分で作り出すことが甘かったということです。では、集中しやすい環境を整えるにはどうすればいいのでしょうか?
5. 集中しやすい環境をつくる方法

集中しやすい環境をつくるには、聴覚や視覚を刺激するものを遮断することです。人の脳は、雑音や騒音があるとそちらに注意が向いてしまいます。音楽やテレビの音、人の話し声などです。
そこで、仕事や勉強を始めるときは、まず音楽やテレビは消しましょう。オフィスや喫茶店など音を遮断することが難しい場合は、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンをしてみるのも手です。さらに、目からの情報で注意が外に向きがちな方は、仕事を妨げない程度のレンズの色が薄いサングラスや色つきメガネに変えてみるのも良い方法です。
もう一つ、集中しやすい環境づくりに大切なことは、途中で邪魔が入らないようにすることです。集中している時に一番の邪魔になるのは、メールやLINE、SNSからの通知ではないでしょうか。これらに邪魔をされると厄介です。
たとえメッセージの返信がすぐに済んだとしても、頭を集中状態に戻すのに30分以上かかることもあるからです。そう考えると、集中している時のメールやメッセージほど怖いものはありません。
- 例えば、朝と晩の2回だけ通知をチェックする
- 集中したいときはスマホの電源をわざわざ切る
など、自分で事前にルールを設定しておくと、いざという時に集中を切らすことがなくなります。
集中しやすい環境には、快適さも大切な要素です。
- 座りにくい椅子
- 寒すぎたり暑すぎたりする部屋
- 窮屈な衣服
これらは長時間の作業に向きません。集中のためにはできるだけなくす必要があります。ちなみに、私が実践している集中するための部屋の環境づくりを、過去にこちらの記事で紹介したので参考にしてみてください。
また、作業の間に身の回りをいい香りにしておくと、適度にリラックスした状態で作業することもできます。一説によると、勉強や仕事には柑橘系の香りが良いと言われています。自分の中でより快適に作業できそうな香りが既にある方は、それで作業するのも良いでしょう。自分の一番好きな香りを選んで、集中できる環境をつくってみてください。
以上、ここまでの紹介の内容をまとめると、
- 自分自身に対する正当な評価をすること
- 世界の頭のいい人は空気を読まない
- 苦手な仕事は他人に振る
- 適度なストレスを与える
- 集中力を身につけない
といったことが、世界に通用する頭のいい人の特徴でしたね。本書「世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた」は著者である中野信子さん本人の経験に基づく内容になっていて、私たちの日常に取り入れやすい方法が多数紹介されています。より深く内容が気になる方は、ぜひ本書を手に取ってみてください!