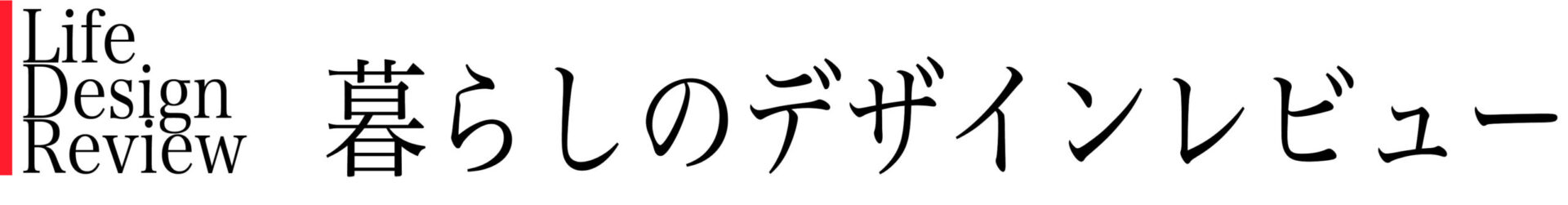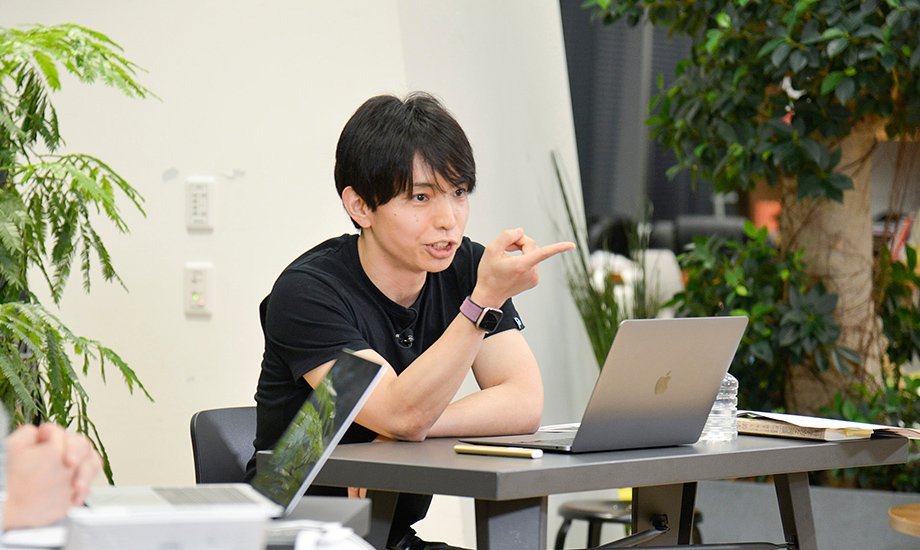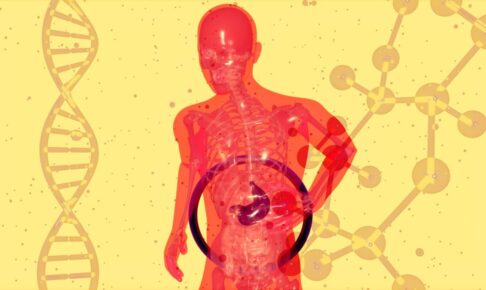画像引用:https://dreamcompasses2.blog.ss-blog.jp/
この記事では、当ブログで今までに紹介してきた鈴木祐さんの書籍をまとめて紹介します。
著者は言わずと知れた科学論文オタク。メンタリストDaigoさんが、日本で一番尊敬している方です。
鈴木さんは、体調管理やアンチエイジング、マインドコントロール、天職の見つけ方など、私たちの日々の生活や悩みに直結するテーマについて、世界中の論文から得た知見を基に、科学的な解決方法を教えてくれてます。
何となく分かっていたけれど、そうだったのかとスッキリする内容が多く、どれも一度は読んでおいて損はないものばかりです。
ぜひ、ざっと目を通してみてください!
1. 最高の体調
「最高の体調」は、文明病という、人間の体の進化が現代社会の発展に追いつけないことで起きる、病気や身体の不調について、科学的なエビデンスをもとに解説しています。その主な原因は、炎症と不安。これらは、激変した現代社会における多すぎるカロリー、過度なストレス、少なすぎる運動や睡眠時間、少なすぎるビタミンや食物繊維の摂取などが原因で、私たちの体を蝕んでいます。
炎症を防ぐ方法は、以下の7つ。
- 腸内環境を整える
- 運動をする
- 自然に触れる
- 良好な人間関係を築く
- よく眠る
- デジタル断食
- ストレスを減らす
具体的なやり方などは、本書や紹介記事を参考にしてみてください。
また、不安はなぜ体に悪いのか。それは、不安は体を戦闘モードにするからです。狩猟採集時代では、不安とは獲物に襲われたときに交感神経が優位になってからだが戦闘モードに入るのが本来の不安の機能。
現代を生きる私たちが、常にぼんやりと不安を抱えているということは、常に体がなんとなく戦闘モードになってしまっていて、体をきちんと休められていない状態です。
このぼんやりとした不安に対しては、以下3つの対策があります。
- 価値観をはっきりさせる
- マインドフルネスになる
- 畏敬の念を抱く
これについても、具体的なやり方などは、本書や紹介記事を参考にしてみてください。
2. 不老長寿メソッド
「不老長寿メソッド 死ぬまで若いは武器になる」はアンチエイジング、いつまでも若々しくいるための方法について書かれた本です。
私たちの体に眠っている回復力が、痛みによって目覚めさせる機能を“ホルミシス”と言い、体が若返る仕組みは、苦痛と回復のサイクルを繰り返すことで成り立つそうです。
つまり、適度な痛みが若返りの“刺激のトリガー”となり、体は若さを取り戻そうとし、機能が向上するのです。ここでの苦痛とは傷つくではなく、運動や効果的な食事、適度なストレス、サウナ(暑さ、寒さ)、ファスティング(断食)などが当たります。
ポリフェノールは実は毒?
野菜や果物などの体に良いとされる食べ物には、豊富な栄養だけでなく、少しの“毒”が含まれています。これが、ホルミシスのスイッチを押す“痛み”に該当します。この毒を総称して“フィトケミカル”言い、植物が自分の体を守るために作り出した成分のことを指します。
有名なものとしては、ポリフェノールのほかに、緑茶のカテキン、大豆のイソフラボン、ブドウのアントシアニン、トマトのリコピン、ニンジンのベータカロテンなどもフィトケミカルであり、実は毒。
体にいい成分は、そのものがいいのではなく、それに体が反応していい効果を生むということです。
このような毒や刺激、苦痛は、適量であればホルミシスを発動させるため、体に有益に働きます。
睡眠・栄養を摂る・休養を取る
また、弱った身体の回復方法は大きく、睡眠・栄養を摂る・休養を取るの3つ。睡眠については、十分な量をとり、かつ質も上げること。
栄養については、栄養価の高い食事を摂ること。そして、休養については、リラックスする時間や趣味の時間などを取ることが大事になります。
また、これらの回復の効果を上げるために押さえるべきコツは、回復に自己コントロール感を持つこと。自分で回復の方法や目的などをデザインし、攻めの姿勢で回復することです。
苦痛と回復の適切な量は個人差があるので、試しながら自分に合うやり方を探していく必要があります。
そこで大事ことは、自分をよく観察すること。体調や気分がどう変化するかを観察することで、自分に合うやり方を探しやすくなります。
苦痛と回復をいろいろ試すにも、選択肢はたくさんあります。その中で、どれから取り組むべきか、データと効果のバランスが良い方法を、本書では4つのロードマップとして紹介しています。
具体的な方法については、本書や紹介記事を参考にしてみてください!
3. ヤバい集中力
仕事に集中できない、勉強が手に付かないなどの悩みを抱える人には「ヤバい集中力」をオススメします。元も子もないですが、集中力という能力は存在しないそうです。
私たちが普段思っている集中力とは、セルフコントロール能力や自己効力感といった複雑なプロセスの全体を何となく“集中力”と呼んでいるに過ぎません。
集中するにはこれらをトータルな枠組みの中で、本能を理性でコントロールする必要があるのです。著者はこの本能を獣と呼び、理性を調教師と呼んでいます。
獣のやる気を上げるには、「報酬の出し方」がポイントです。獣は報酬の額で釣るのではなく、報酬を“予感させる”ことで釣るのです。
獣は課題が難しすぎると、頑張ってもゲットできそうにないから放っておこうとなり、課題が優しすぎると、いつでもゲットできそうだからやはり放っておこうとなります。
そこで、ちょっと頑張れば手に入りそうな報酬を予感させる設定が必要になります。これにより、獣をやる気にさせることができるのです。想像してみてください。仕事をしていて、これは全く意味がないという課題はやる気が出ませんよね。
同じく、あまりにも難しい課題に対してもやる気が出ません。ちょっと頑張ればできそうな課題は、今にもやる気が出てきそうになりませんか?
本書では、その他にも獣をやる気にさせる方法や、調教師(理性)の能力を上げる方法が書かれています。そして、どうしても集中できない時のとっておきの方法は、諦めること。実は集中力をキープするには、物事を諦めることが欠かせません。
集中力が続かない人は、集中力を追い求め過ぎる傾向にあります。あまりに集中力を求めすぎると、調教師が自分には能力がないと考えてしまいます。
これが繰り返されるとアイデンティティに刻み込まれてしまい、マイナスの自己像が出来上がってしまうので、集中力を持続させるには、時に諦めることも重要です。
4. 科学的な適職
「科学的な適職」では、自分にぴったりの仕事を選ぶための5つのステップが紹介されています。これらのステップを実行すれば、適職に就ける確率が上がるというのが本書の主張です。
いまの仕事を、好きだから、お金が稼げるから、流行りだからといった理由で選んでしまっている方に、ぜひ読んでほしい一冊です。
ここでは、私たちが適職探しで陥りがちな、よくある間違い“7つの大罪”と、逆に仕事の幸福度を決める“7つの徳目”をまとめて紹介します。
7つの大罪
- 好きを仕事にする
- 給料の多さで選ぶ
- 仕事の楽さで選ぶ
- 業界や職種で選ぶ
- 性格テストで選ぶ
- 直感で選ぶ
- 適性に合った仕事を求める
仕事選びにおける7つの大罪は、一見間違っていなそうなものもある、職業選びの際り陥りがちな罠です。本書や紹介記事を参考に、自分が当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。
7つの徳目
自分の未来を広げるための、仕事の幸福度を決める“7つの徳目”は、自由、達成、焦点、明確、多様、仲間、貢献の7つです。私たちはこれらの条件を満たす仕事を選べば、幸福になれます。
これらについても、本書や過去の紹介記事を参考に、自分の仕事や転職したいと思っている仕事が、当てはまるのかどうかチェックしてみてください。
本書ではその他にも、最悪な職場に共通する8つの悪や、正しい仕事を選ぶことができなくなるバイアス(バグ)を取り除くためのテクニック、仕事の満足度の判断方法などが紹介されています。
気になる方は、ぜひ手にとってみてください!
5. 無 最高の状態
「無 最高の状態」は、不安・怒り・孤独・虚無・自責から、自らを解放する科学的メソッドが紹介されています。孤独感、うつ、不安、完璧主義など、これらは現代人の心の機能不全です。
原始仏教の経典には、ゴータマ・ブッダの言葉として「一般の人と仏弟子の違いは、二の矢が刺さるか否かだ」。悟りを開いた人間でも、実際には喜怒哀楽の感情を持つ点では、常人と変わらない。
すべての生物は生存に伴う根本の苦難からは逃れらない。この絶対的な真実を、1本目の矢が刺さった状態と例えています。多くの人は自ら二の矢を放って、苦しみを高めてしまっているのです。
これを、専門用語では“反芻思考”と言います。
怒りを6秒やり過ごす
一の矢だけで苦しみを終えれば、“苦”に縛られることはありません。また、近年の研究では、一の矢の脅威が思ったより長く続かないことがわかってきました。私たちの怒りは、せいぜい6秒しか持続しないそうです。
つまり、反射的な6秒をやり過ごしさえすれば、一の矢の痛みは過ぎ去ります。それにもかかわらず、私たちが悩みを引きずるのは、二の矢を自で放つからです。
怒りの感情が生まれたら、まず何もせずに6秒待ってみることは、二の矢を刺さないためにすぐにできる有効な手段です。
また、ネガティブな思考はどれも、自己をベースに広がり始めます。放っておけば静まるはずだった嫌な感情を、増大させます。そして、自己を中心に思考が過去と未来に向けて広がると、さらに事態は悪化します。
「私は1ヶ月前も似たようなことで怒られた。」「私の未来は一体どうなるのか。」このように、すべての苦しみは自己の問題に行き着きます。
目の前に存在しない過去と未来の脳内イメージが、私たちを二の矢で貫いているのです。同じようなトラブルでも、苦しむ人と苦しまない人がいるのは、メンタルが強いか弱いかの問題ではないということです。
これは、脳内で作られた独自のストーリーラインが、適用か否かの問題です。本書では、自己とは何かについての解説から、私たちを悩ませる脳内シミュレーションをなくす無我の導入方法まで、科学的に展開されています。
本書や紹介記事を参考に、無我を達成するための精神修養の技法を取り入れてみてください!
6. YOUR TIME ユア・タイム
「YOUR TIME ユア・タイム 4063の科学データで導き出したあなたの人生を変える最後の時間術」は、「時間不足から脱却できない」と悩んでいる方に向けて、時間術の3つの真実に迫りながら、本当に効果的な時間術を探求しています。
まず著者は、現代人が時間不足から脱却できない原因は、時間術における以下3つの真実に隠されていると言い、これまでの時間術を真っ向から否定しています。
時間効率を気にしていたら、作業効率は下がるし時間をマネジメントしようなんて発想は無理で、ほとんどの時間術は時間の使い方と無関係だそうです。
- 真実1:時間術を駆使しても仕事のパフォーマンスはさほど上がらない
- 真実2:時間の効率を気にするほど作業の効率は下がってしまう
- 真実3:時間をマネジメントするという発想の根本に無理がある
“予期”と“想起”の調整
これらの真実を踏まえて、あなたにあった時間術を見つける方法として、本書では“予期”と“想起”の調整を提案しています。
予期は未来、想起は過去と関係しています。未来は今の状態の次に起きる確率が高い変化を、脳が予期したもの。過去は今の状態の前に発生した確率が高い変化を、脳が想起したものです。
例えば、あなたの目の前に泣いている女の子がいたとします。その女の子を見てあなたは、いつかはこの女の子は泣き止むだろうと思い、泣き止むまでそばにいてあげようと思ったとします。これが、予期です。
同じように、あなたの目の前に泣いている女の子を見て、もしかして親とはぐれちゃったのかなと思ったとします。これが、想起です。
つまりあなたは、泣いている女の子を見た時に“予期”と“想起”の両方が起こり、こんなところで一人で泣いているということは、きっと迷子になって困っているから一緒にいてあげようと判断したのです。
ここでのポイントは、予期も想起も確率が高いことをあなたが選んでいるに過ぎないということ。
これらの確率を上げる方法として本書では、
- タイムログを付ける
- カレンダーに遡って予定を書く
- タイムボクシングを使う
といった方法が紹介されています。
人は往々にして作業がはかどった時のことばかりを思い出して時間配分を決めがちなので、タイムログに記録して、普段は例外として無視しがちなトラブルも含めた時間を書き出し、想起の精度を上げていくことが特に有効です。
本書や紹介記事には、たくさんの時間術がそれぞれの症状を別に紹介されているので、時間に悩む全ての現代人におすすめです!
7. 運の方程式
近年の研究では、成功は大半が能力よりも、運で決まると言われています。
それなら、頑張っても無駄だと思うかもしれませんが、運はスキルを伸ばすことによって、掴みやすくなることが分かってきています。
本書は、まさにその方法について解説されています。「運の方程式」では、まさにその方法について解説されています。
本書では“運の方程式”として、
幸運=(行動×多様+察知)×回復
が紹介されています。またこれを基に、それぞれの要素、行動・多様・察知・回復を高めるためにできることを書かれています。
物事の成果は「試行回数×成功率」で決まるので、“行動”が大事なのは納得できますよね。
その他にも、試行回数の作用を十分に活かすには同じことを繰り返すのではなく、バリエーション(多様)も増やす必要があり、身の回りで起きる小さな変化に気づく能力(察知)も、良い偶然を開花させる働きがあります。
多様について
ここでは、多様について、簡単に紹介しておきます。
運をつかむために人間関係が欠かせないことは直感的にわかりますが、旧友から思わぬ情報が手に入ったり、飲み会の出会いが新たな仕事に結びついたりと、予期せぬ幸運の大半は、他者からもたらされます。
つまり、運には社会的ネットワークが大切です。
そう言われても、新しい人との出会いがない、自分には狭い交流しかない、コミュニケーションが下手などど落胆する人もいるかもしれません。人間関係が重要だと言われて、そう簡単に改善できるなら苦労はありませんよね。
幅広い付き合いの大事さは分かっていても、つい馴染みの仲間とばかり時間を過ごしてしまうケースは多いでしょうが、気落ちする必要はありません。
なぜなら、社会的ネットの幅を広げる能力も、トレーニングで伸ばせるスキルだからです。
本書で紹介されている具体的なアクションリストを実際に試してみることで、科学的に運気を上げることができるでしょう。